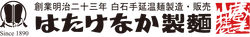白石温麺(しろいしうーめん)について

日本一短い麺「白石温麺」
白石温麺(しろいしうーめん)は全国でも珍しく、わずか9cmの長さでちょっと太めのそうめんです。油を使わない製法でからだにやさしく、短くて食べやすいのが特徴です。
「温かい麺」と書くので冬の食べ物だと思われますが、地元宮城県白石市では春夏秋冬一年中食べられます。夏は水でしめて冷たいつけつゆで、冬は温かくしてかけうーめんで、炒めものにしたり、味噌汁、サラダ、鍋の〆、なんでもござれの万能麺。
短くて食べやすく独特の歯ごたえがあって毎日食べても飽きの来ない白石温麺は、白石市民がこよなく愛するソウルフードなのです。

親孝行から生まれた「白石温麺」
宮城県白石市は蔵王山麓の山々に囲まれ、緑豊かな大地に清らかな水と澄んだ風が通り抜ける自然豊かな町です。江戸時代には白石城の城下町としても栄え、伊達政宗の側近片倉小十郎が治めておりました。
温麺の発祥は400年ほど昔の藩政・元禄時代にさかのぼります。当時の白石城下に鈴木味右衛門という孝行息子がおりました。味右衛門は胃を病んで何日も絶食し寝込んでいた父親に何か良い食事はないかと悩んでいたところ、旅の僧から油を使わない麺の製法を教わり、苦心の末会得したその麺をつくって食べさせたところ、父親は快方に向かいました。
この孝行話が時の白石城主片倉小十郎公に伝わり献上したところ、みちのくの人の温かい思いやりをたいそう賞でられ、「温麺(うーめん)」と名付けられました。白石温麺は子供が親を思う温かい心から名付けられた麺なのです。

からだにやさしく食べやすい9cm
白石温麺は表面の乾燥を防ぐための油を使わず、小麦粉と水と塩だけでつくります。油を使わないので胃にやさしく、上品な味わいで藩主伊達家から大名や公家への贈答品としても用いられました。9cmという長さは、献上する際に馬の背に積んでも折れにくくした為と言われています。お子様やお年寄りでもすすりやすくて食べやすく、何よりシコシコとした食感とのど越しも、この長さ9cmから生まれます。

7日は白石温麺の日
蔵王山麓の豊かな自然が生んだ美しい水が豊富な白石には、白石和紙、小原の葛、そして白石温麺の三つの名産品があります。清らかな水が流れるこの風土だからこそ生まれたこの三つの名産は「白石三白(しろいしさんぱく)」と称されたほどでした。
時代は流れ三白のうち和紙と葛は商業としての生産が途絶えてしまいましたが、白石温麺は現在もこの土地で伝統を守り続けています。2014年4月には白石市が条例を制定し、7月7日の「乾麺の日」にならって、毎月7日を「温麺の日」に定め、白石温麺のPRと消費拡大に努めています。

つなげていきたい、次の世代へ
全国でも珍しいこの長さ9cmの「白石温麺」は400年という長い歴史の中で、有数の麺産地と評される時代もありました。しかし時代の移り変わりと白石の人口減少に伴い徐々に生産量が減り、製造所も減り、今となっては「温麺」は読み方も知らないひとの方が多いかもしれません。
それでもはたけなか製麺はひたすら美味しい白石温麺づくりを追求してきました。明治二十三年に創業してから百三十余年、毎日毎日天候と小麦粉に向き合い、試行錯誤しながら、欠かさず製麺技術を磨き上げてきました。
「最適の材料を使い、ていねいな仕事を心がける」
技術だけではない、思いをこめた麺づくりを通して、多くの方々に笑顔と喜びをお届けしたい。そうしてつくった白石温麺のおいしさを全国の皆様に知ってもらいたい。
そういう思いでつくりあげた、はたけなか製麺の白石温麺をぜひご賞味ください。